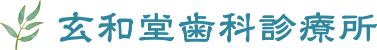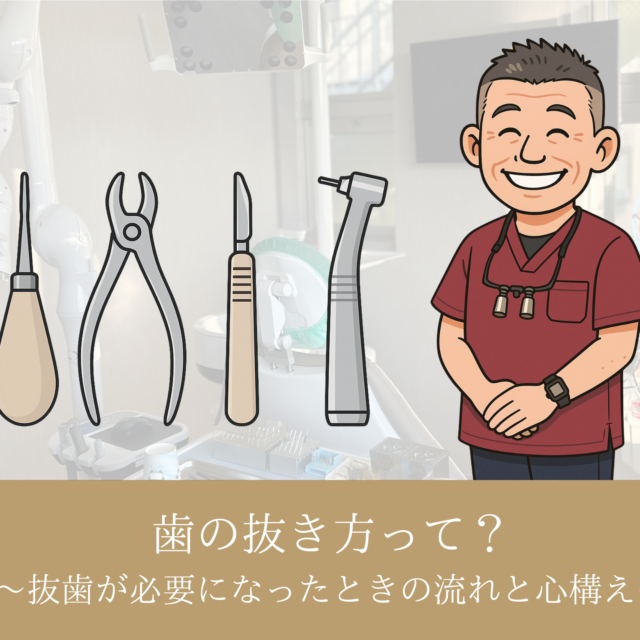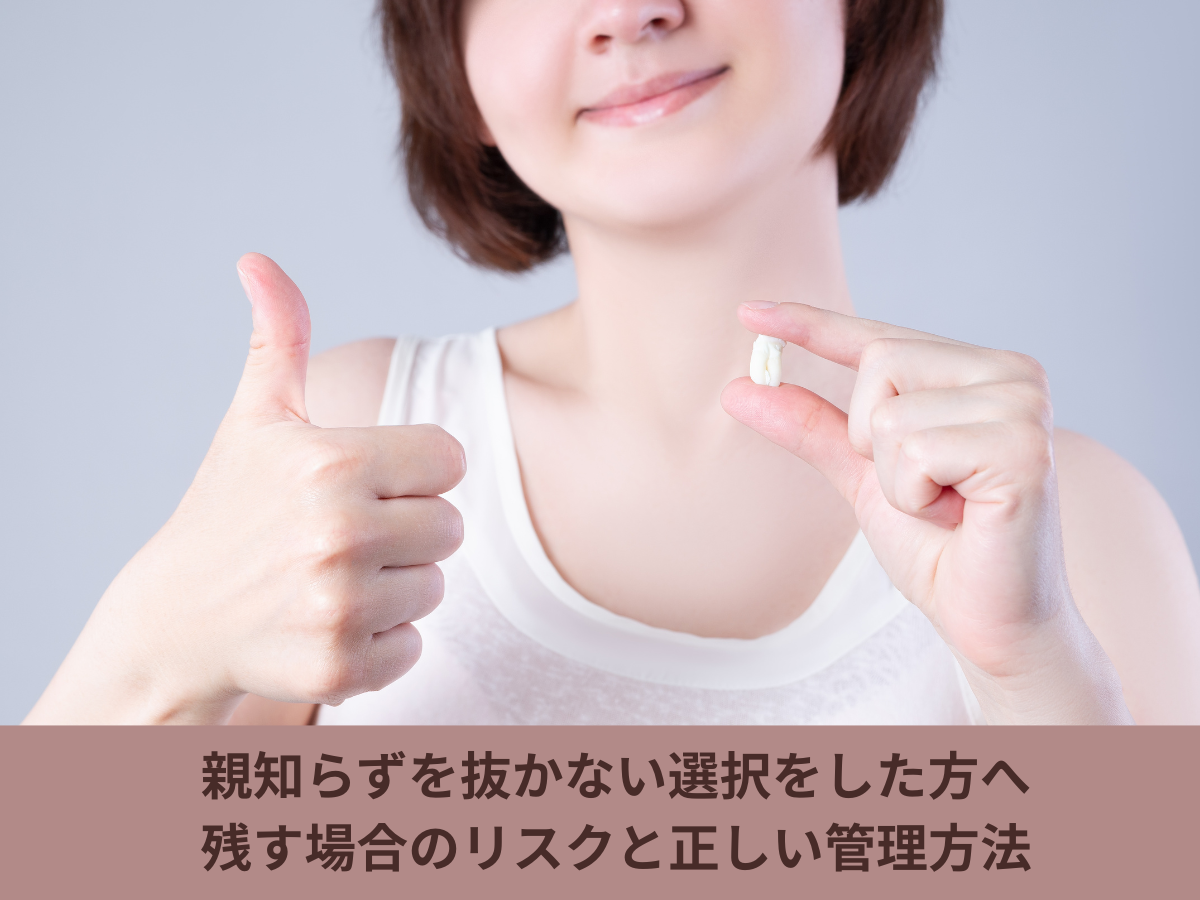
こんにちは。学芸大学駅から徒歩2分の玄和堂歯科診療所です。「親知らず=抜かなければいけない」と思っている方も多いのですが、実は残しておいても問題ないケースもあります。まっすぐ生えていて噛み合わせに支障がなかったり、歯磨きがきちんと行える状態であれば、そのまま経過を観察することも選択肢のひとつです。ただし、**親知らずを残すと決めた場合には、日々のセルフケアと定期的なチェックが欠かせません。**今回は「親知らずを抜かない場合に気をつけるべきこと」についてご紹介します。
親知らずを残すケースとは
親知らずを残してもよいと考えられるのは、次のような条件がそろっているときです。
◆ まっすぐに生えていて、上下の歯の噛み合わせに問題がない
◆ 奥まで歯ブラシが届きやすく、清潔を保てる
◆ 隣の歯や歯ぐきに悪い影響を与えていない
◆ 歯肉や骨に炎症の兆候が見られない
残す場合に注意したいリスク
一見「大丈夫そう」に見えても、親知らずは位置的にトラブルが起きやすい歯です。
▶ 奥にあるため歯ブラシが届きにくく、磨き残しから虫歯や歯周病になりやすい
▶ 食べ物が詰まりやすく、口臭の原因になることがある
▶ 将来的に歯ぐきの腫れや炎症が出やすい
特に大人になってからの親知らずの痛みは、「ズキズキと奥の方から響くような痛み」や「徹夜明けの頭痛が歯ぐきに集中している感じ」と表現されるほど強いことがあります。痛み止めが効きにくく、日常生活や仕事に支障をきたすケースも少なくありません。
親知らずを残す場合のケア方法
「残す」と決めたからこそ、日々のケアと歯科での定期チェックが重要です。
◆ 毎日のセルフケア:奥まで歯ブラシをしっかり届かせましょう。特にワンタフトブラシやデンタルフロスを使うと清掃効果が高まります。
◆ 定期検診でのチェック:目では見えなくても、レントゲンで初期の虫歯や炎症が発見されることがあります。半年に一度は歯科で確認するのがおすすめです。
◆ プロフェッショナルケア:親知らずの周囲はバイオフィルム(細菌の膜)が残りやすい部分です。歯科医院でのクリーニングを受けることで、家庭のケアでは落としにくい汚れを効果的に除去できます。
こんな症状が出たらすぐに相談を
次のようなサインが出たら、放置せずに歯科を受診してください。
▶ 奥の歯ぐきが腫れてズキズキする
▶ 強い口臭を感じるようになった
▶ 噛んだときに違和感や痛みがある
▶ 奥歯の間に食べ物がよく詰まる
痛みが出てからでは治療が大掛かりになりやすいため、**「痛くなる前に定期的なチェックを受けて予防する」**ことが何より大切です。
まとめ
親知らずを抜かない選択は間違いではありません。ただし、それは**「残しても管理ができる状態」**であることが前提です。毎日の丁寧な歯磨きに加え、定期検診とプロケアを続けることで、親知らずを健康に保つことができます。玄和堂歯科診療所では、患者さまの親知らずの状態を丁寧に確認し、一人ひとりに合った管理方法をご提案しています。気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
監修:院長 寺師 史峰(歯科医師)
関連記事のご案内
親知らずについてさらに詳しく知りたい方は、こちらもご覧ください。
▶ 親知らずの抜歯について
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 親知らずを残しておくと、どのくらいの頻度で歯科に通えばよいですか?
A. 半年に一度の定期検診をおすすめします。状態によっては3〜4か月ごとのチェックが安心です。
Q2. 親知らずの周囲が少し腫れたり、痛んだりした場合はどうすればいいですか?
A. 一時的に症状が治まっても、炎症のサインかもしれません。早めに歯科医院での受診をおすすめします。
Q3. 親知らずの周囲は歯磨きがしにくいのですが、効果的な道具はありますか?
A. ワンタフトブラシやデンタルフロスを使うと、奥の細かい部分まで清掃しやすくなります。

 WEB予約
WEB予約