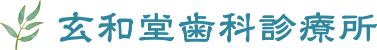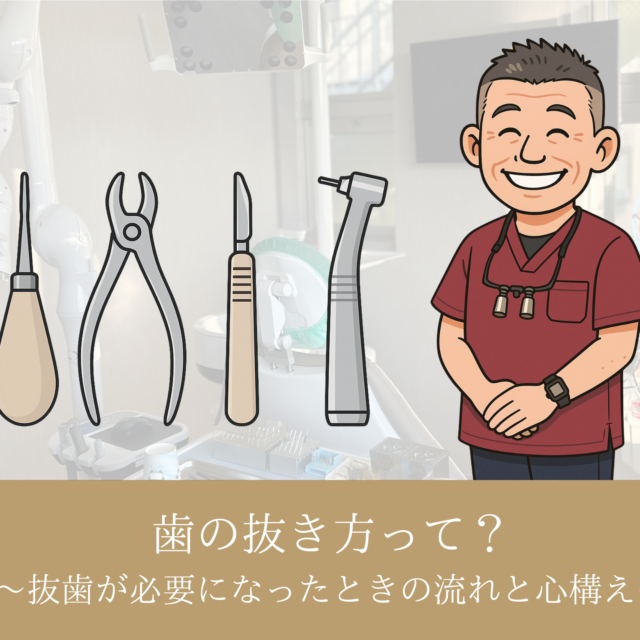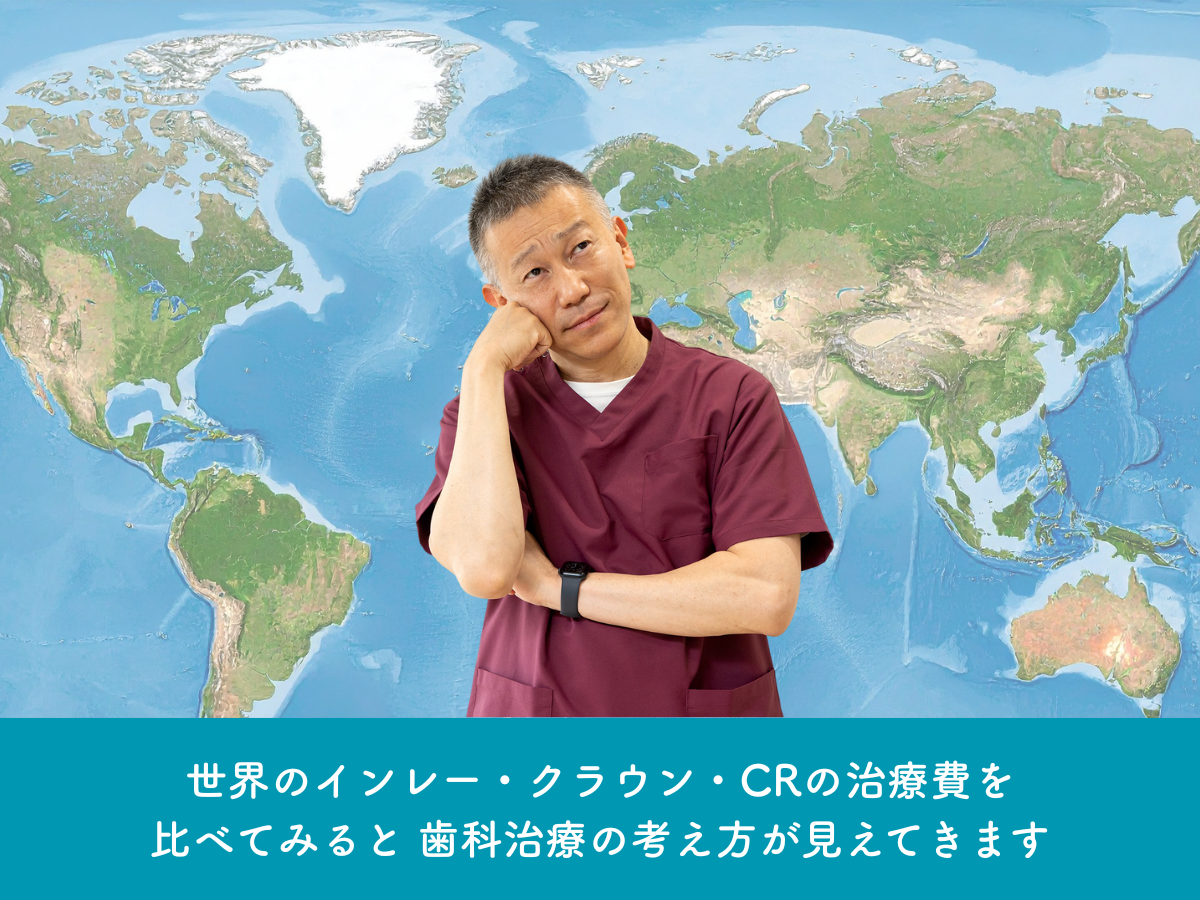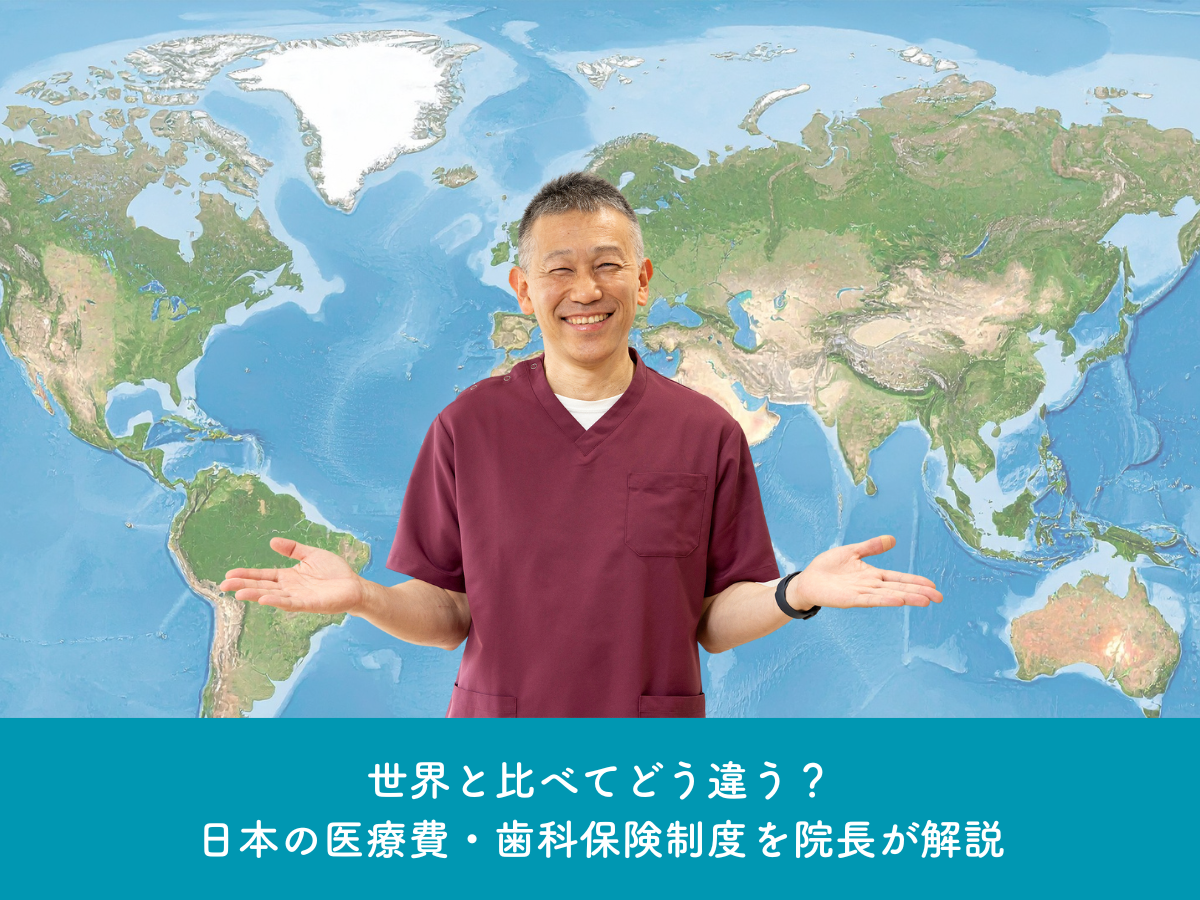目次
こんにちは。学芸大学駅から徒歩2分の玄和堂歯科診療所です。
「食べるたびに口の中がヒリヒリ…」
「しみて痛くて食事がつらい…」
そんなお悩みを抱える方に向けて、今回は**“食べ物からできる口内炎対策”**についてお話しします。
当院には、口腔の健康だけでなく全身の健康を支える視点から、「薬膳マイスター」の資格を持つスタッフが在籍しています。
今回はそのスタッフ監修のもと、口内炎の予防・改善につながる食材や食生活のヒントを、歯科医療の視点とあわせてご紹介します。
■ 口内炎ってなぜできるの?
口内炎の原因にはさまざまなものがあります。
✔ストレスや疲労による免疫力の低下
✔栄養バランスの偏り(特にビタミンB群の不足)
✔誤って頬や舌を噛むなどの外的刺激
✔矯正装置や合わない詰め物による慢性的な刺激
✔ウイルス・カビによる感染(ヘルペス性・カンジダ性など)
「たかが口内炎」と思われがちですが、日常生活の質を大きく下げてしまうこともあります。
胃腸の弱りが口内炎に?東洋医学の視点から
漢方の考え方では、胃腸の調子が落ちている状態を「**脾(ひ)**が弱っている」と表現します。
口内炎ができやすい方は、まさにこの「脾」の働きが低下しているサインかもしれません。
お口は“身体の入り口”。
胃腸がうまく働かないと、どんなに良い食事をとっても、エネルギーをしっかり作り出すことができません。
その結果、栄養が体のすみずみに届かず、むくみ・鼻水・痰などの不要物として溜まってしまうこともあるんです。
■ 食べ物でできる口内炎対策とは?
痛みを和らげながら、体の内側から改善をめざしましょう。
🟢 口内炎におすすめの食材(薬膳マイスター監修)
-
ビタミンB2・B6が豊富な食材:レバー、卵、納豆、バナナ、牛乳
-
粘膜修復を助ける緑黄色野菜:にんじん、ほうれん草、ブロッコリー
-
腸内環境を整える食品:ヨーグルト、味噌、ぬか漬けなどの発酵食品
-
体の熱を冷ます作用のある食材:きゅうり、大根、トマト、緑茶など
口内炎は「体に熱がこもっている状態」と東洋医学的に捉えることもあり、熱を冷ます食材を上手に取り入れるとよいとされています。
🔴 控えたほうがよい食材・刺激物
-
唐辛子やわさびなどの香辛料
-
酸味の強い柑橘類や酢
-
熱すぎる料理や飲み物
-
かたくて鋭い食感のもの(トースト、スナック菓子など)
■ 日常でできるケアのポイント
-
歯ブラシで傷つけないよう、柔らかいブラシを使う
-
アルコール成分のないマイルドなうがい薬を使う
-
口腔用の保湿ジェルや軟膏タイプの市販薬を活用する
-
ストレスと睡眠不足を避けることも大切です
■ 病院に相談したほうがいいのはこんなとき
-
2週間以上治らない
-
繰り返し何度もできる
-
出血・しこり・腫れなどがある
-
発熱やリンパ節の腫れを伴う
「長引く口内炎=大きな病気のサイン」ということもあります。
お口の粘膜に関する不安がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
食事と生活習慣が、お口と身体を元気にします!
いくら良い食材を取り入れても、暴飲暴食や睡眠不足、味の濃い食事が続くと「脾」の力は弱まってしまいます。
まずは、規則正しい生活とバランスの取れた食事を意識することが、口内炎予防の第一歩です。
そして何より大切なのが、お口の健康=全身の健康ということ。
毎日のセルフケアに加えて、定期的に歯科医院でのチェックやクリーニングを受けることもお忘れなく!
ご不安なことや「最近、口の中が荒れやすいかも?」と感じることがあれば、いつでもお気軽に玄和堂歯科診療所へご相談くださいね。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 薬膳的におすすめの食材はありますか?
A. はい、きゅうり・トマト・緑茶など「熱を冷ます」食材や、粘膜を修復する緑黄色野菜、発酵食品が効果的です。
Q2. 食事以外でできるセルフケアはありますか?
A. 柔らかい歯ブラシや低刺激のうがい薬、保湿ジェルの使用が推奨されます。十分な睡眠も大切です。
Q3. 口内炎がよくできるのは病気ですか?
A. 繰り返す口内炎は、栄養不足やストレス、口腔内のトラブルが関係していることがあります。一度歯科で相談するのがおすすめです。
📍玄和堂歯科診療所(公式サイトはこちら)
-
住所:〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-16-18 ASAX学芸大学ビル(旧鷹番Kビルディング)303号室
-
アクセス:東急東横線「学芸大学駅」東口より徒歩約2分
-
診療日:月・水・木・土・日(火曜・金曜・祝日は休診)
-
診療時間:
-
午前 9:30~13:00
-
午後 14:30~18:30
-
-
電話番号:03-6452-3882

監修|院長
寺師 史峰
本記事は、【口内炎】(食事・いたみ・食べ物)について、一般的な歯科情報としてまとめたものです。
症状やお口の状態により必要な対応は異なりますので、ずっと治らない口内炎や発症を繰り返す場合などは歯科医院へご相談ください。
▶ 院長プロフィールを見る
人気の記事
最近の投稿

 WEB予約
WEB予約